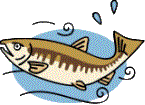|
魚いお のはなし 鮭川(さけかわ)のかおり |
|
私たちには馴染みの深い鮭なのですが、世界に視野を広げた場合にはごく限られた地域でしか繁殖していないことが知られています。 回遊性なだけに到るところで捕獲されますが、こと繁殖に限っては北半球の北緯30度から70度の河川流域に限定されるのです。 それは落葉広葉樹の生息帯と重なることが判明しています。 |
|
落葉広葉樹の極相種であるブナや近種の多様な広葉樹とその混交林(中間地帯)とは、 この分解有機物や微生物群が母川の生態系により異なっていることが、ふるさとおふくろの香りの違いとなり鮭の嗅覚識別の基としての役割を担っていると考えられています。
|
|
■さけかわとさーもんぴんく サケが好んで回帰する母川とは、いったいどんな要素を持ち合わ
|
■生成物の搬送役
日本の川は時に"滝である(Stream )"と表現されるほどに急峻な勾配の印象が持たれます。源流から海域までが諸外国の悠然たる川(River )とはかけ離れていることからですが、この河川地形が母川としての恩恵をもたらしています。 村上市の北部を流れる三面川は、東北南部のブナ原生林である朝日連峰の源流から海までの河川距離が41kmであり、流域にダム以外の障害物や水質汚染源もなく、さらに源流のみならず流域各地にもブナ林が点在しています。そしてブナ林の豊富な生成物が希釈されることなく、そのままそっくり海へと注いでいます。河川分類上は二級河川であり短距離なだけに深い大河とはならず、むしろこれが幸いとなる第一級の鮭川要因といえます。実際10〜5km未満の小川や澤が幾筋も存在しています。 さらに日本海側はしばしば山を降りたところがすぐに海である、と表現されるところが少なくありませんが、海寄りの山北さんぽく村沿岸に至っては川を形成する間もなくブナ林の源流が沁み水として、海へと注がれる地形環境が森林帯分布図からも読み取れるほどです。 こうした天賦の恵みが注がれた沿岸の代表的景勝地笹川流れに至っては海域一帯が鮭を呼び寄せている、といった表現も大袈裟とはいえないでしょう。鮭以外の貝や海草や魚類も豊富でかつ新鮮で滋味にあふれた状態で、周年にわたり生息してゆけるのは鮭川の最大の恩恵といえます。
|
|
■ブナの分解者たち 大量の有機生産物を林床に提供するブナは、木質は茸菌類に、樹皮や葉は青カビ菌類によって分解されていきます。さらに有機酸や無機酸となり水に溶け運ばれていくと考えられます。その他ブナ林に集まる小動物もソースやキャリアとして循環的に包括されてゆくので、計り知れない生産量となってゆきます。        |
|
■ アスタキサンチン アスタキサンチンは、自然界が生み出す代表的な色素カロチノイドの一種で、キサントフィル類の仲間で す。β-カロチンなどと同じ仲間で、サケ・エビ・カニや海藻などの魚介類に多く含まれる赤橙色素です。その抗酸化力はビタミンEの1000倍にも達し、「史上最強のカルチノイド」と言われています。つまり血中脂質の活性酸素を抑え、血管を若々しく保ったり、免疫細胞を活性酸素から守ることで免疫力を高めます。魚介類に多く含まれるルテイン・リコペン・β-カロチンといった抗酸化物質としてのカロチノイドは、生物が活性酸素から自分を守るために身につけたと考えられます。 「サケは泳ぐ栄養カプセル」(鈴木平光・徳立行政法人食品総合研究 |
|
■ アスタキサンチンも旅をする ヘマトコッカスなどの緑色藻類内で生成されるアスタキサンチン色素は、藻に紫 外線が照射されると一週間以内には藻自身を覆う勢いで鮮やかな赤橙色に染め 上げていきます。それが食物連鎖によりオキアミやサクラエビなどの体に蓄えられ、 さらにサケや大型生物に捕食されます。サケはこれを体内の主に筋肉に蓄えて遥 か北洋から帰還する長旅の、激しい代謝をサポートするスタミナ源として活用しま す。この活性色素は繁殖が近づくとオスは表皮へメスは卵巣へと移行させます。こ れは婚姻色の体表や筋子やイクラを美しく彩ってゆき次世代への活力として引き 継がれていきます。 自然産卵の環境では繁殖を終えたサケの身は、ホッチャレとなり河川流域に留ま り生態系で分解されます。さらにその分解栄養素が土地を養育し林を形成したあ と、再び朽ちて分解され川に運ばれ海に注がれ、次の連鎖のスタート地点に戻っ て旅を続けていきます。
|
|
■ サーモンピンクはアスタキサンチンの色 サケはもともと白身の魚なのです。稚魚が降海し海中の微小プランクト ンを捕食し成長していきながら北洋域に達すると、そこには動物性プラン クトンであるナンキョクオキアミが豊富に生息しています。 このナンキョクオキアミを捕食することで、そこに含まれる赤橙色のアス タキサンチン色素と本来の淡黄色の白身が混ざり合い、お馴染みの サーモンピンクの優しい色調が形成されるのです。アスタキサンチンはサ ケ以外でもタイやキンメダイ、カニやエビの甲羅にも含まれますが、サケ ほど多く含む魚はいないとされ、これはまさにサケ特有の色といえます。 <アスタキサンチン含有量>ベニザケ(野生):3.68mgギンザケ(野生):2.26mgキングサーモン: 0.86mgシロザケ:0.37mgイクラ・スジコ:0.8mgクルマエビ:0.62mgケガニ:1.11mg ※クルマエビ・ケガニは甲殻を含みません。
|
|
お客様の声(鮭) 冬は鮭の季節です 鮭料理 鮭製品販売コーナ |
|
越後村上うおや サイト 0254-52-3056 https://www.uoya.co.jp |